 見沼区障害者生活支援センター やどかり
見沼区障害者生活支援センター やどかり 大宮区障害者生活支援センター やどかり
大宮区障害者生活支援センター やどかり 浦和区障害者生活支援センター やどかり
浦和区障害者生活支援センター やどかり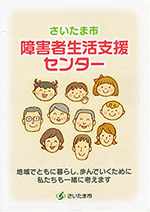 |
さいたま市が発行するパンフレットです. パンフレットでは,さいたま市10区の障害者生活支援センターが紹介されています.ご相談のある方は,お住まいの区の支援センターにお電話ください.必要に応じて面談や訪問等でお話を伺います. |
| 配置 | 研修名称 | 受講修了人数 |
|---|---|---|
| 浦和区障害者生活支援センターやどかり | 埼玉県相談支援従事者専門別コース研修(地域移行支援)/平成30年度 | 1人 |
| 埼玉県相談支援従事者専門別コース研修(地域移行・定着)/令和4年度 | 1人 | |
| 主任相談支援専門員研修/令和3・4年度 | 2人 | |
| 強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)/令和4年度 | 1人 | |
| 見沼区障害者生活支援センターやどかり | 埼玉県相談支援従事者専門別コース研修(地域移行支援)/平成30年度 | 1人 |
| 主任相談支援専門員研修/令和4年度 | 1人 | |
| 大宮区障害者生活支援センターやどかり | さいたま市精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修/令和6年度 | 1人 |
さいたま市障害者生活支援センター運営業務自己採点表
2023年度
2022年度
2024年度事業計画
相談支援活動
障害のある人や家族からの相談に対応し,それぞれが抱えるニーズを丁寧に導き出し,個々が希望する暮らしが実現できるよう支援体制づくりを行う.障害福祉サービスのみならず,地域のさまざまな資源や人とのつながりをつくり,暮らしを支える環境を整えていく.
また,2024年度はさいたま市から障害者生活支援センターの委託期間が満了となるため,次年度以降の委託を受けるためのプロポーザル方式による選定が行われる.障害者生活支援センターの事業を継続していくために,選定の準備を行う.一方で委託相談支援事業が消費税対象事業であるとされている問題については,市内受託法人との情報交換などを行い,対応していく.
1)各区の地域ネットワークづくり
2024年度は,新たに見沼区にて基幹相談支援センターを受託する.すでに受託している浦和区と併せ,地域の実情に応じたネットワークづくりを推進し,障害のある人や世帯の実態から,必要な支援環境の在り方をさまざまな関係者と議論していく.また,さいたま市地域協議会連絡会議とも連動し,さいたま市自立支援協議会への課題解決に向けた提案を行う.
2)地域移行支援の取り組みを具体的に進める
精神科病院からの地域移行を具体的に進める取り組み行う.他の自治体の取り組みを学ぶなど,ピアサポーターとともにこれからの地域移行の進め方について具体的な対策を検討していく.
2023年度事業報告
相談支援活動
1.相談支援活動の総括
浦和区・大宮区・見沼区それぞれの障害者生活支援センター(以下,生活支援センター)は,さいたま市からの委託を受け,地域の一次相談窓口として,障害のある人やその家族の相談に対応した.また,ニーズに合った支援が提供されるよう,関係機関への連絡調整やケア会議の開催等行い,他機関と連携して支援する態勢を整えた. 現在,さいたま市では,障害者支援地域協議会(以下「地域協議会」/現在浦和区含め6区で実施.その他の区も実施に向け準備中)を軸とした地域の支援態勢の仕組みづくりが進められている.浦和区,大宮区,見沼区それぞれの地域の実情に合わせ,地域課題の抽出とネットワークづくりを支援課や関係機関と共に進めた.
1)新規相談者の状況
2023年度の新規相談件数は239件(浦和区78件,大宮区67件,見沼区94件).在宅中心の生活にある人に関する相談が,例年同様6割以上にのぼる.生活支援センターへの新規相談は,サービス等利用計画作成依頼とその他の相談とに大別される.サービス等利用計画作成は,主に通所事業所を利用するための計画作成や,家事援助等を利用するための居宅介護事業所の選定と計画作成に対応した.一方で,市内全域にわたって,福祉サービスの利用希望者数に対して相談支援事業所が不足しており,利用者自身がサービス利用計画を作成(セルフプラン)する割合が増えている.さらに,ヘルパー不足により対応できる事業所も少なく,家事援助の利用に時間がかかることが多い.制度があっても十分に機能していない状況がある.
その他の相談では,さまざまな相談が寄せられた.本人や家族からの相談は,精神的な不調から通院がままならない状況にあるなど,既存の支援では解決の見通しがつきづらいものも多く,足掛かりとして訪問看護を選択肢とすることが増えている.一方で支援機関からつながる相談では,家族間の問題や生活上の課題に加えて,障害特性によるコミュニケーションの難しさなど,課題は複合的だ.また,親が亡くなった後の支援や,高校卒業後の支援など,警察や学校から,地域支援の主軸の役割を期待される相談もある.さまざまな機関がニーズを掴む一方,掴んだニーズに十分に対応可能な,地域の支援態勢とネットワークの構築は今後の課題である.
2)継続相談者の状況
継続相談者数は783人(浦和区274人,大宮区217人,見沼区292人).電話や面接,訪問等で延べ9,152件の相談に対応した.この他,計画相談支援におけるサービス利用計画作成とモニタリングによる訪問や面接を行った.相談者の平均年齢は48.3歳.継続相談者の生活基盤の状況は図1~3に示す.
最も多い支援は,電話による本人や家族への相談対応,次いで関係機関との連絡調整等である.訪問や面接,同行などの支援は全体の2割弱であった(図4).内容は「福祉サービス利用」に関するものが約半数を占める.事業所内での人間関係における悩みや困りごと,利用の仕方,事業所探しや見学,関係機関や家族との情報共有などに対応した.
(1)日常に埋もれる生活課題への支援
何らかの福祉サービスにつながっている人の中には,事業所や訪問看護の職員との日常的な関わりや相談を通して,本人にはあたり前で意識しづらい課題や権利侵害が発見されることがあった.借金問題や健康問題,家族との関係や介護,ライフステージの変化に伴い発生する課題に対し,法律相談や医療機関,家族等の支援者とも連絡を取り合いながら,事業所と協力して支援態勢を整えた.詐欺や暴力などの犯罪に巻き込まれている人もおり,安全を確保できる環境整備を行った.
(2)つながりづらい人たちのへの支援
社会的な支援につながらないまま,親も本人も高齢化した「8050世帯」に地域包括支援センターや支援課といっしょに訪問した.親は,「親亡き後」を心配しつつも,現状を変えることは負担が大きい.各区で取り組む「つながり支援会議」で世帯の困難さを共有し,きょうだいなどキーパーソンがいる場合,協力して親や本人への情報提供を行った.また区ごとに開催される,主に未治療で生活が困難な状況にある人を対象とした「さいたま市精神障害者訪問支援事業」に参加し,医療機関やこころの健康センター等の専門機関と連携して対象者への支援を行った.継続した関わりを通して状況に変化が見られる人もおり,専門的で多角的な視点のアセスメントと細やかな支援の重要性も見えてきた.
「8050世帯」をはじめ,社会的支援につながらないまま困難さが恒常化している世帯の背景にある課題として,家族に支援を過剰に依存した制度と,「家族の支援は家族がすべき」という社会的期待がある.それは家族が本人の支援を抱え込まざるを得ない状況を生む.まずは,本人と家族が支援につながりたいと思えるための十分な情報提供や,家族支援が重要だ.また,ライフステージを通じて適切な時期に適切な支援が,途切れることなく提供される支援態勢をつくる必要がある.
3)虐待・差別への対応
虐待相談では,世帯内における不適切な関わりなどに対応した.本人が家族と離れることを希望しないことも多く,訪問や福祉サービスの導入を通して世帯内の風通しをよくし,支援機関で連携して生活状況の把握を行った.差別相談では,内科疾患の手術治療に対し,精神科がないため対応できないと拒まれたとの相談があった.近年,このような相談は減少していたものの,民間の医療機関全てで,精神疾患をもった人があたり前に手術を受けられる状況にはまだない.今後市民会議等を活用し,現状の共有が必要だ.
4)各区の取り組み
(1)浦和区の取り組み
① 地域ネットワークづくり
基幹相談支援センターを受託して3年目となり,主に浦和区障害者支援地域協議会(以下区協議会)の運営,サービス調整会議・相談支援連絡会議の開催,区内障害福祉サービス事業所への訪問,さいたま市障害者支援地域協議会連絡会議(以下協議会連絡会議)への参画等に力を入れて取り組んだ.
浦和区支援課及び浦和区障害者生活支援センターむつみとの緊密な連携のもと,区協議会,サービス調整会議や相談支援連絡会議の事務局を担い,円滑に会議を開催できるよう取り組んだ.区協議会では,世代別ワーキンググループを中心とした交流や学習の機会を持ち,区全体では介護者支援についてのシンポジウムを開催した.また,区協議会で整理した地域課題を協議会連絡会議で他区と共有し,さいたま市自立支援協議会で報告した.サービス調整会議では,事例検討やつながり支援会議を行い,区内地域包括支援センターとの共同作業により,支援が途切れやすい状況にある障害のある人や世帯を図で表し,重点的に取り組むべき支援目標について整理した.その他,基幹相談支援センターとして地域の指定特定相談支援事業所等への事業所訪問を行い,今後の浦和区のネットワークのあり方について意見交換を行った.
② 権利擁護の取り組み
指定特定相談支援事業所とともに,障害のある人の権利擁護について考えるため,滝山病院事件や優生保護法裁判について情報提供を行い,意見交換を行った.また,虐待対応については,浦和区支援課及び権利擁護支援員,さいたま市権利擁護センター等と連携し,迅速な対応を行った.
(2)大宮区の取り組み
① 地域ネットワークづくり
大宮区支援課と大宮区障害者生活支援センターみぬまと協働し,サービス調整会議,相談支援連絡会議を毎月開催した.サービス調整会議では事例検討やつながり支援会議,地域協議会についての検討などを行った.相談支援連絡会議は,大宮区内の指定特定相談事業所に加え,他区の指定特定相談支援事業所8か所も出席し,計画相談支援利用者の状況の共有や引継ぎ,事例検討を通して相談支援の質を高め合う機会とした.
また,「大宮区地域で支えるネットワーク会議」は運営委員会を毎月開催し,全体会を9月と2月に大宮区役所会議室にて開催した.それぞれ36事業所から53人,37事業所から50人が参加した.9月は地域協議会についての行政説明と他区の取り組みの報告,2月は大宮区内の事業所の実践報告を行った.毎回グループ討議を行い,それぞれの事業所の現状や課題を共有した.事業所間連携が大切であるという共通認識ができてきた.終了後には同会場で情報交換会の場を設け,参加者それぞれに交流の輪を広げる機会となった.
② 権利擁護の取り組み
さいたま市誰もが共に暮らす市民会議とさいたま市グループホーム職員研修に,権利擁護支援員として運営に協力した.それぞれの参加者が人権や権利侵害,虐待や差別などについて学びを深められるよう取り組んだ.
(3)見沼区の取り組み
① 地域ネットワークづくり
支援課,障害者生活支援センター来人と協力し,「見沼区障害者支援地域協議会準備会」を2回開催し,地域協議会実施体制の検討や児童期と高齢期の支援態勢について意見交換を行った.10月に区内事業所へのニーズ把握のためのアンケート調査を実施,2月には「事業所情報交換会」を開催.児童期の支援体制や災害時対応などの課題が浮き彫りとなった.また区内地域包括支援センター職員との意見交換会を実施し,8050世帯を取り巻く課題を共有した.今後はネットワーク会議やワーキングの設置を目指していく.
サービス調整会議(隔月1回)では,こころの健康センターなど専門機関を加えた事例検討,つながり支援会議では,対象者の課題の再整理と重点的に支援する事例を洗い出し,困難な状況にある人の支援がより前進するよう会議内容を見直した.相談支援連絡会議(月1回)では事例検討や学習会を行った.また,区内の相談支援事業所1か所が閉所し,相談支援事業所不足の課題に直面し,2024年度への継続課題となった.
② 権利擁護の取り組み
恒常的なセルフネグレクトに陥っている世帯や虐待リスクの潜む世帯に対し,支援課とともに状況の把握を行った.権利擁護センターの助言を得て,世帯への働きかけを続け,想定される緊急時の対応等検討した.
5)さいたま市の相談支援態勢づくり
障害のある人が安心して暮らせるよう地域課題の解決に向け,さいたま市自立支援協議会(専門部会含む)の委員として活動した.また,障害者生活支援センター連絡会議に参加し,障害のある人を中心とした相談支援態勢づくりに向け,教育研修や調査研究,権利擁護など各委員会にて,支援の質の向上や課題整理に取り組んだ.
地域移行・地域定着支援では,連絡会議に参加し,COVID-19を踏まえた精神科病院の現状を共有した.市内精神科病院へのニーズ調査を計画したものの実施できなかったため,2024年度への継続課題となった.
各区の取り組みを進める中で,児童期支援や8050世帯の問題,社会資源の不足や職員の人材不足など,各区共通した課題が見えてきた.今後さらに各区の実態把握と課題の抽出を行い,施策課題としての議論につなげていきたい.また,10月に厚労省から自治体へ,委託相談支援事業は課税対象であり非課税とするのは自治体の誤認であるとの通知が示された.さいたま市では,委託相談支援事業に営利法人は参入できず,生活支援センターは近年ますます,公的責任で担うべき役割を負っている.相談支援事業は社会福祉の根幹であり,営利事業とする国の仕組みには異を唱えていかなければならない.一方で市内には,営利法人の運営する福祉サービス事業所の割合が9割を超える区もあり,利用者を顧客と見立て,経営都合が優先される実践が懸念される.各区のネットワークづくりを通して,障害のある人や家族の実態から学ぶ土壌をつくっていきたい.
